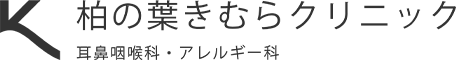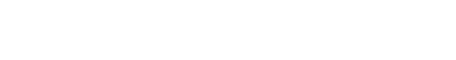- 喉・首のよくある症状
- 性咽頭炎・急性扁桃炎
- 慢性咽頭炎
- 声帯ポリープ・声帯結節
- 咽喉頭逆流症(LPRD)
- 咽頭がん・喉頭がんなどの腫瘍性病変
- リンパ節の腫れ(反応性リンパ節炎)
- 唾液腺炎・唾石症
- 甲状腺の病気
- 頚部の良性腫瘤
喉・首のよくある症状
 このような症状は、風邪や疲労による一時的なトラブルのこともありますが、実は慢性的な炎症や腫瘍など、早期発見・治療が必要な病気が隠れていることもあります。
このような症状は、風邪や疲労による一時的なトラブルのこともありますが、実は慢性的な炎症や腫瘍など、早期発見・治療が必要な病気が隠れていることもあります。
喉や首は、話す・飲み込む・呼吸するという日常動作に関わる非常に大切な部分です。
「違和感はあるけれどそのままにしている」という方も、症状が長引いたり繰り返したりしている場合は、耳鼻咽喉科での診察をおすすめします。
こんな症状はありませんか
- 喉が痛い
- 喉に違和感がある・異物感
- 飲み込みにくさがある
- 声が出にくい
- 声枯れ・声がかすれる
- 咳が出る
- 痰・血痰が出る
- 息苦しい
- 食事中にむせる
- 味が分からない
- 口内炎ができた
- 舌に違和感がある、腫れ
- 首にしこりがある
急性咽頭炎・急性扁桃炎
のどが強く痛み、赤く腫れる「急性咽頭炎」「急性扁桃炎」は、ウイルスや細菌感染が原因で起こります。
特に扁桃腺が腫れて膿がつく「化膿性扁桃炎」では、高熱や全身のだるさを伴い、抗菌薬や吸入などの治療が必要となることがあります。
早めに治療すれば数日で改善することが多いですが、放置すると「扁桃周囲膿瘍」などに進行し、入院による処置が必要となるケースもあるため注意が必要です。
慢性咽頭炎
「のどがイガイガする」「つかえる感じがする」「ずっと軽く痛い」などの症状が数週間以上続く場合、慢性咽頭炎が疑われます。
声の使いすぎ、喫煙、口呼吸、空気の乾燥、アレルギー、胃酸の逆流などが原因で、咽頭粘膜が慢性的に刺激を受けて過敏になった状態です。
この病気は完全に治るまでに時間がかかることも多く、症状に応じて生活指導や内服治療を継続的に行うことが必要です。
声帯ポリープ・声帯結節
「声が枯れる」「歌うと声が出にくい」といった症状が続く場合は、**声帯にできる病変(ポリープや結節)**の可能性があります。
とくに教師・保育士・接客業・歌手など、日常的に声を多く使う方に起こりやすく、炎症が長引くと手術が必要になるケースもあります。
声のかすれを軽視せず、早めに耳鼻咽喉科で評価を受けることが大切です。
咽喉頭逆流症(LPRD)
胃酸や消化酵素が食道を越えて喉の奥(咽頭・喉頭)まで逆流し、炎症を起こす病気です。胸やけなどの典型的な逆流性食道炎の症状が目立たないことが多く、「喉のつかえ、違和感がある」「原因のはっきりしない咳や声のかすれが続く」というケースで見落とされやすいのが特徴です。症状が慢性的に続く場合は、内服治療と生活習慣の見直し(食後すぐに横にならない・就寝前の食事を控えるなど)が重要です。
咽頭がん・喉頭がんなど
の腫瘍性病変
喉頭がんや咽頭がんは、のどの粘膜にできる悪性腫瘍で、初期には声のかすれやのどの違和感、飲み込みにくさなど、風邪に似た軽い症状しか出ないこともあります。
特に喫煙や飲酒の習慣がある方はリスクが高いため、「声が枯れて戻らない」「のどの違和感が2週間以上続く」といった場合は、早めに耳鼻咽喉科で内視鏡検査を受けることをおすすめします。喉頭がんや咽頭がんは早期発見で治療の選択肢が広がる病気です。気になる症状が続く場合には、自己判断せず専門医の診察を受けましょう。
リンパ節の腫れ
(反応性リンパ節炎)
風邪やウイルス感染のあとに、首のリンパ節が一時的に腫れることはよくあります。
通常は1〜2週間で自然に治まりますが、「腫れが引かない」「しこりが固い・大きい」といった場合は、別の病気が隠れている可能性があります。
悪性リンパ腫やがんの転移といった疾患の初期所見として現れることもあるため、早めの受診が大切です。
唾液腺炎・唾石症
顎の下(顎下腺)や耳の下(耳下腺)にある唾液腺に炎症が起きると、首やあごの下が腫れ、痛むことがあります。
特に唾石症では、食事のたびに腫れや痛みが悪化するのが特徴です。炎症が繰り返されると慢性化することもあります。
甲状腺の病気
(バセドウ病・橋本病・腫瘍など)
のどの下あたり(のどぼとけの下)にある甲状腺が腫れると、前頸部にふくらみや圧迫感、異物感を感じるようになります。
甲状腺はホルモンを分泌する臓器であり、腫れの原因としては良性の腫瘍、ホルモン異常(バセドウ病・橋本病)などが考えられます。
血液検査・超音波検査などを組み合わせた診断が必要です。
頚部の良性腫瘤
(のう胞・脂肪腫・
唾液腺腫瘍など)
頚部に現れるしこりの多くは良性で、**先天性のう胞(正中頚のう胞・側頚のう胞)や脂肪腫、唾液腺腫瘍(耳下腺・顎下腺)**などが代表的です。
特に唾液腺腫瘍は無痛性で進行がゆっくりなため、長年気づかれないこともありますが、まれに悪性の場合もあるため注意が必要です。
しこりの性状や経過に応じて、必要に応じた評価を行います。