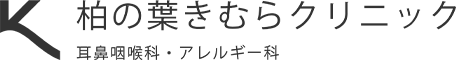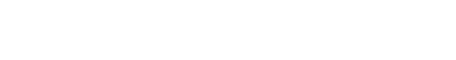鼻のよくある症状
このような症状が長く続く方は鼻炎や副鼻腔炎の疑いも考えられます。
少しでも症状が見られましたら当院までご相談ください。
- 鼻が痛い
- くしゃみが出る
- 鼻血が出る
- 水っぽい鼻水がでる
- 色の付いた鼻水が出る
- 粘り気の強い鼻水が出る
- 鼻が詰まっている
- 鼻水が喉へ流れ落ちる
- 頬や眉の周辺が痛む
- 鼻から不快な臭いがする
- 嗅覚障害(臭いが感知できない)
風邪による急性鼻炎
急性鼻炎は、風邪のウイルスによって鼻の粘膜に炎症が起こる病気です。症状としては、ヒリヒリとした鼻の痛みや違和感、乾燥感、くしゃみ、鼻水、鼻づまりなどが挙げられます。治療には、鼻の内部の通気性を改善する処置や、ネブライザー治療による炎症の抑制が行われます。
副鼻腔炎(蓄膿症)・鼻茸
風邪の症状が長く続くと、鼻や副鼻腔が炎症を起こし、膿のような鼻水、頭痛、頬や目の奥の痛みなどが起こることがあります。急性上気道炎や鼻炎と区別するのは難しいため、レントゲンやCT検査を行い、副鼻腔に液体が溜まっていないかを確認します。治療は、鼻の処置や抗生剤の服用が中心ですが、薬を服用しても改善できない場合は手術を検討します。急性副鼻腔炎が慢性化すると慢性副鼻腔炎へ移行するリスクが高くなるため、放置は禁物です。
アレルギー性鼻炎
 アレルギー性鼻炎には、サラサラした水っぽい鼻水、鼻詰まり、くしゃみという特徴的な症状が見られます。サラサラした鼻水は何度かんでも止まらず、日常生活に悪影響を及ぼすことがあります。
アレルギー性鼻炎には、サラサラした水っぽい鼻水、鼻詰まり、くしゃみという特徴的な症状が見られます。サラサラした鼻水は何度かんでも止まらず、日常生活に悪影響を及ぼすことがあります。
アレルギー性鼻炎は、特定のシーズンに症状が現れる季節性アレルギー性鼻炎と、どの季節でも症状が現れる通年性アレルギー性鼻炎に大別されます。
季節性アレルギー性鼻炎には花粉症があり、早春から春に飛散する、スギやヒノキの花粉によるものが有名です。また、カバノキ科・イネ科の植物やヨモギ・ブタクサなど、初夏や夏、秋に飛散する花粉によって起こる花粉症もあります。
一方、通年性アレルギー性鼻炎は、ダニやハウスダスト、ペットのフケや唾液・毛、真菌(カビ)、化学物質などがアレルゲンとなる病気です。ダニアレルギーは基本的に通年性とされていますが、秋に症状が悪化するため、「秋の花粉症」と誤解されることもあります。
鼻中隔弯曲症
鼻中隔は左右の鼻の穴を隔てる部分で、外見上は真っ直ぐな鼻筋に見えても、実際には左右どちらかに曲がっていることが多いです。この弯曲が大きくなり、強い鼻詰まり(鼻閉)を引き起こし、鼻呼吸がうまくできなくなった場合、鼻中隔弯曲症の診断がつきます。
鼻中隔弯曲症では、慢性的な鼻詰まりや慢性副鼻腔炎を併発しやすく、鼻血(鼻出血)が何度も出たり、嗅覚障害などの症状が現れたりすることもあります。慢性的な鼻詰まりや鼻血、副鼻腔炎が頻繁に起こっている場合は、鼻中隔弯曲症の手術を受けると、鼻詰まりが解消したり副鼻腔炎の再発リスクが軽減されたりする効果に期待できます。
鼻出血
出血の程度は一人ひとり異なっており、血が滴る程度の軽いものから、数時間止まらない出血まで様々です。はっきりとした原因は未だに不明ですが、寒い時期や乾燥している時期に発生しやすく、小さな子どもや高齢者によく見られる傾向があります。
出血が起こる箇所の中で特に多いのは、鼻中隔の入口付近(キーゼルバッハ領域)です。この部分の粘膜は血流が豊富なため、粘膜に傷がつくと出血します。
鼻出血があった場合は、少し前かがみになり、鼻翼(小鼻の柔らかい部分)を指でつまんだ状態で、20〜30分ほど安静にしてください。
嗅覚障害
風邪やアレルギー性鼻炎、慢性副鼻腔炎、鼻中隔弯曲症などが原因で「におい分子」が嗅上皮まで届かなくなると、臭いを感知できなくなります。また、風邪のウイルスなどによって嗅細胞そのものが傷つくと、高度な嗅覚障害が起こるようになります。
検査では、まず鼻の中を観察してから、レントゲン検査やCT検査などの必要な検査を実施します。
治療するには、鼻の処置、投薬、手術などによって、嗅覚障害を引き起こしている病気を治すことが必要です。