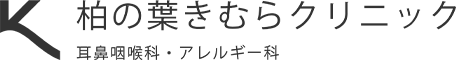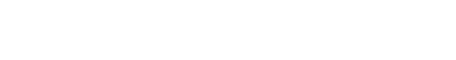耳のよくある症状
 このような症状は、日常的に起こりやすいものですが、放っておくと悪化したり、慢性化したりすることもあるため注意が必要です。
このような症状は、日常的に起こりやすいものですが、放っておくと悪化したり、慢性化したりすることもあるため注意が必要です。
耳の症状は、外耳・中耳・内耳・聴神経などさまざまな部位の異常が原因となって起こるため、早めの対応が大切です。
こんな症状はありませんか
- 聞こえにくい、耳がつまった感じがする
- 耳鳴りがする(キーン、ジー、ザーなど)
- 耳が痛い
- 耳がかゆい
- 耳だれが出る
- 耳垢がつまっている
- 補聴器を検討している、補聴器の聞こえ方に不安がある
- めまいやふらつきがある
これらの症状がひとつでもある場合は、耳鼻咽喉科での診察をおすすめします。
急性中耳炎
急性中耳炎は、鼻や喉の風邪をきっかけに、鼻と耳をつなぐ耳管を通じて細菌やウイルスが中耳に入り、炎症を起こす病気です。特に小さなお子さまは耳管が短く太いため、感染が起こりやすく、耳の痛みや発熱、不機嫌、耳だれなどの症状が見られます。
適切な抗生物質治療で多くは改善しますが、治りきらずに繰り返すと滲出性中耳炎や慢性中耳炎へ進行することがあります。
滲出性中耳炎
滲出性中耳炎は、中耳の中に液体(滲出液)がたまる病気で、急性中耳炎のあとに続けて起こることもあります。痛みや発熱といった強い症状はほとんどなく、「聞こえにくさ」だけが長く続くため気づかれにくいのが特徴です。
特に小児では、言葉の発達や集中力に影響を与えることもあるため、学校や園での聴き取りづらさがあれば早めの受診が大切です。
外耳炎
外耳炎は、耳の穴(外耳道)に炎症が起こる病気で、綿棒や耳かきによる耳掃除のしすぎや、湿度・汗などの刺激によって皮膚のバリアが傷つくことが原因です。
耳の痛みやかゆみ、耳だれが見られ、悪化すると外耳道が腫れてふさがってしまうこともあります。
治療は抗菌薬やステロイドの点耳薬を中心に行い、患部を刺激しないことが回復の鍵です。
耳垢栓塞
(じこうせんそく)
耳垢栓塞は、耳垢(みみあか)が耳の中で硬く固まり、耳の穴をふさいでしまう状態です。聞こえにくさ、耳のつまった感じ、耳鳴りを引き起こすことがあります。
ご自身で取ろうとすると奥に押し込んでしまい、悪化することもあるため、耳鼻科での安全な除去をおすすめします。
突発性難聴
突発性難聴は、ある日突然、片方の耳が聞こえなくなる病気で、原因ははっきりしていませんがウイルス感染や内耳の血流障害、ストレスなどが関与すると考えられています。
放置すると聴力が回復しないこともあるため、できるだけ発症から48時間以内の治療開始が望ましいとされています。
軽い耳の違和感だけでも、気づいたらすぐに受診することが大切です。
耳鳴り
耳鳴りは、「キーン」「ジー」「ザー」などの音が、実際には音がしていないのに聞こえてしまう症状です。加齢、ストレス、疲労、騒音曝露、内耳や聴神経の障害など、さまざまな要因が関係します。
耳鳴りの裏に難聴が隠れていることもあるため、まずは聴力検査などで原因をしっかり調べることが重要です。治療では生活指導や音響療法、必要に応じて薬物療法を組み合わせます。
耳管狭窄症・耳管開放症
耳管とは、鼻の奥と中耳(鼓膜の内側)をつなぐ細い管で、中耳の換気や気圧調整に重要な役割を果たしています。この耳管の働きに異常が起きると、「耳がつまった感じ」や「自分の声が耳に響く(自声強調)」、「気圧の変化で耳が痛くなる」などの不快な症状が現れます。
- 耳管狭窄症では、アレルギー性鼻炎や上咽頭炎、風邪の影響などで耳管が腫れて通りが悪くなり、耳閉感や軽い難聴、めまい感などが生じます。
- 耳管開放症では、耳管が本来閉じているべきときにも開いたままになり、自分の声や呼吸音が響く、不快感が続くといった症状が起こります。
体重減少、脱水、ホルモン変化、ストレスなどがきっかけになることがあります。
いずれも鼻や喉と連動するため、耳鼻咽喉科での包括的な評価と治療が重要です。鼻内処置や点鼻薬、生活指導などで改善が見込めるケースもあります。
内耳性めまい
(良性発作性頭位めまい症
・メニエール病など)
内耳には「三半規管」「前庭」といった平衡感覚をつかさどる器官があり、ここに異常が起こるとめまいが生じます。
代表的なのが「良性発作性頭位めまい症(BPPV)」で、寝返りや起き上がりなど頭の動きに伴って回転性のめまいが生じるのが特徴です。
また「メニエール病」は、めまいに加えて耳鳴りや難聴を伴い、内耳のリンパ液の循環異常が原因と考えられています。
症状に応じて、生活指導、薬物療法、リハビリなどを組み合わせて治療します。