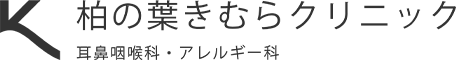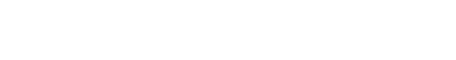慢性副鼻腔炎とは
 慢性副鼻腔炎(まんせいふくびくうえん)は、鼻の奥にある「副鼻腔」に炎症が長期間にわたって持続する病気で、一般的には「蓄膿症」と呼ばれます。
慢性副鼻腔炎(まんせいふくびくうえん)は、鼻の奥にある「副鼻腔」に炎症が長期間にわたって持続する病気で、一般的には「蓄膿症」と呼ばれます。
通常の風邪や急性副鼻腔炎が数週間で治癒するのに対し、12週間以上症状が続く場合を慢性副鼻腔炎と診断します。
炎症が慢性化すると、副鼻腔の粘膜が腫れたり、換気・排泄路が狭くなったりして膿や粘性の分泌物がたまりやすくなります。これにより、鼻づまり・後鼻漏・嗅覚障害などが持続し、QOL(生活の質)を大きく損ないます 。
主な症状
- 膿性鼻汁(黄色〜緑色で粘り気がある)
- 強い鼻づまり(片側・両側)
- 鼻水が喉へ流れる(後鼻漏)
- 顔面痛・頭重感(頬・額・眼の奥など)
- 嗅覚障害(匂いが弱い/全くわからない)
- 慢性的な咳や痰
これらは「ただの鼻風邪」と区別がつきにくいことがありますが、長引く場合は精密な検査が必要です。
発症のメカニズム(病態)
慢性副鼻腔炎では、副鼻腔の換気不良が病態の中心となります。
- 副鼻腔の出口(自然口)が狭窄・閉塞
- 換気や排泄が障害され、分泌物が停滞
- 線毛運動が障害され、分泌物が停滞
- 停滞した分泌物に細菌・炎症が加わり、慢性化
この「換気不良 → 分泌物の停滞 → 炎症の持続」という悪循環が、慢性副鼻腔炎を形成します。
また、鼻中隔弯曲症や下鼻甲介肥大などの構造的要因 、アレルギー性鼻炎による粘膜腫脹 も関与し、炎症が長引きやすくなります。
診断方法
慢性副鼻腔炎は臨床症状だけでは診断が難しいため、以下の検査を組み合わせて行います。
- 鼻内視鏡検査
鼻腔内を直接観察し、膿性分泌物や粘膜腫脹の有無を確認。鼻茸(ポリープ)の存在も評価。 - CT検査
副鼻腔の炎症範囲や貯留液、構造的異常を三次元的に把握。 - アレルギー・血液検査
IgEや好酸球数を測定し、アレルギーの関与を評価。 - 嗅覚検査
においの自覚障害を客観的に評価。慢性副鼻腔炎では嗅覚障害が持続することが多い。
治療方針
慢性副鼻腔炎は「段階的治療」が基本です。
薬物療法(保存的治療)
- 抗菌薬(マクロライド系を少量・長期投与することが有効とされる場合あり)
- ステロイド点鼻薬(局所の炎症を抑制)
- 抗ロイコトリエン薬(アレルギー性炎症が背景にある場合)
- 内服ステロイド(重症時に短期間使用)
これらを組み合わせ、炎症を鎮めて副鼻腔の自然排泄を促します。
鼻洗浄
食塩水による鼻洗浄は、膿やアレルゲンを洗い流し、薬物療法の効果を高めます。
手術療法
(内視鏡下副鼻腔手術:ESS)
薬物療法で改善しない場合、**内視鏡手術(ESS:Endoscopic Sinus Surgery)**を行います。
- 副鼻腔の換気・排泄路を広げ、炎症組織を除去
- 膿や病的粘膜を除去し、薬剤の効果が届きやすい環境に改善
- 病態に応じて、鼻中隔矯正術や下鼻甲介手術を併用することもある
当院では全身麻酔下の日帰り手術に対応し、手術から回復まで専門医・麻酔科医が連携して安全に行っています 。
鑑別すべき疾患
慢性副鼻腔炎と似た症状を示す疾患も存在します。
- 真菌性副鼻腔炎:副鼻腔内に真菌が繁殖し、菌球を形成。片側性が多い。
- 歯性上顎洞炎:虫歯や歯科治療に関連して上顎洞に炎症が波及。片側の鼻症状や頬部痛を伴う。
- 副鼻腔腫瘍:鼻閉・鼻出血・顔面腫脹などを呈することがあるため、CT・病理検査で鑑別。
これらの疾患が疑われる場合には、耳鼻咽喉科と歯科・口腔外科・頭頸部外科の連携が重要です。
当院の特徴
柏の葉きむらクリニック耳鼻咽喉科では、
- 内視鏡・CTを用いた精密診断
- 薬物療法から手術療法まで一貫した治療体制
- 歯性上顎洞炎などの歯科領域疾患との連携診療
- 術後も継続的に行う再発予防とフォローアップ
を重視し、患者さまにとって最適な治療を提供しています。
受診をおすすめする方
- 鼻づまりや膿性鼻汁が3か月以上続いている
- 匂いがわかりにくい、または完全に消失している
- 片側の鼻づまり・頬の痛みがある
- 薬で改善しないため手術を検討している
慢性的な鼻の症状は、放置すると再発や進行を繰り返します。
「ただの鼻づまり」と思わず、お早めにご相談ください。